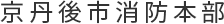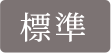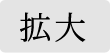令和4年 フォトブログ
年末特別火災予防運動/年末警戒を実施!
本格的な冬を迎え、暖房器具など火気を使用する機会が多くなり、火災が発生しやすい時期となりました。また、年の瀬の慌ただしさから、火に対する警戒心もついつい緩みがちになります。
消防本部と消防団では、市民のみなさまに今一度、職場やご家庭で「火の用心」への意識を高めていただき、火災のない年末を過ごしていただくため、「年末特別火災予防運動/年末警戒」として街頭での防火広報や車両による巡回パトロールを行い、火災予防を呼びかけます。
住宅防火における「いのちを守る10のポイント」を実践し、1年を「火の用心」で締めくくりましょう!!
◎年末特別火災予防運動(消防本部)令和4年12月20日(火曜日)~31日(水曜日)
◎年末警戒(消防団)令和4年12月28日(水曜日)・29日(木曜日) 20時~22時
令和4年度 署内火災防御訓練を実施
11月29日(火曜日)、火災出動時の指揮隊と消防隊の連携を主眼に置いた火災防御訓練を行いました。
訓練は木造住宅で火災が発生したとの想定で行われ、消防隊が逃げ遅れ者の救出や周囲の建物への延焼防止などを実施しました。
指揮隊は情報収集と安全・確実・迅速な部隊運用を行い、各隊との連携を強化することで災害対応能力の向上を図ることが出来ました。
高規格救急車を更新!
消防本部は令和4年11月28日(月曜日)、総務省消防庁の寄贈救急自動車事業により、一般社団法人日本損害保険協会から高規格救急車の寄贈を受け、峰山消防署久美浜分署の救急車を更新し運用を開始しました。
寄贈を受けた救急車は、最新鋭の安全装備や高度な救命処置を行うための資器材を備えており、適切な救命処置並びに迅速な病院搬送による傷病者の救命率の向上や後遺症の軽減が期待されます。
更新した救急車を適正かつ有効に運用し、本市の救急業務の高度化、救急業務体制のさらなる充実に努めてまいります。
事業所と市消防本部の合同消防訓練を実施!
市消防本部は秋の火災予防運動初日の11月9日、峰山町長岡地内の「株式会社積進 本社工場」において、事業所内で発生した火災を想定し消防訓練を事業所従業員と合同で行いました。
訓練内容は従業員が非常ベルの鳴動により事業所内の火災を発見。従業員による初期消火を実施中に、通報を受けた市消防本部は消防隊を出動させ消火活動を実施。その後、消防隊が屋内検索を行い、建物内に取り残された要救助者を救出しました。
令和4年度京都府消防職員意見発表会に出場!
令和4年11月4日に開催された令和4年度京都府消防職員意見発表会に市消防本部の代表として職員1名が出場し入賞を受賞しました。
消防職員意見発表会とは職務を通じての体験、業務に対する提言や取り組むべき課題などについて自由に発表し、消防業務の諸問題に関する一層の知識の研さんや意識の高揚を図ることを目的として、毎年、開催されています。
発表内容は「経験を伝える」という標題で、現場活動中にあった経験に対し自己に対する反省や課題についての今後の対策や公務災害をどのように防げばいいかといった内容で、周りの雰囲気に惑わされることなく堂々とした態度で発表していました。
危険物移動タンク貯蔵所に対する街頭検査を実施!
令和4年11月1日(火曜日)、京丹後警察署と合同で危険物移動タンク貯蔵所(タンクローリー)に対する街頭での検査を実施しました。
危険物施設には、取り扱いや貯蔵、運搬等に対して消防法により厳しい基準が定められており、適正な維持管理が求められます。
危険物施設の中でも「移動タンク貯蔵所」は、危険物を積載し公道を走行する危険物施設であるため、「いつ」、「どこ」で事故が発生するかわかりません。
街頭検査を行い、災害発生の未然防止や被害を最小限に抑えるため、消防法に定められた基準を満たしているかどうかを厳しく審査し、指導を行いました。
令和4年 秋の火災予防運動
市消防本部・消防団では、11月9日から11月15日まで「秋の火災予防運動」を行います。
住宅防火対策に重点を置き、街頭広報や消防車両での巡回パトロールなど、さまざまな行事を通して市民のみなさんに「火の用心」を呼びかけます。
日ごとに寒さが増し、暖房器具を使う機会が多くなります。暖房器具の使用前点検を行い、使用中はまわりに燃えやすい物を置かないようにしましょう!
◎令和4年度全国統一防火標語「お出かけは マスク戸締り 火の用心」
災害現場を想定した研修会を開催
消防本部は11月2日、京都府内消防本部の職員対象に、自然災害時の救助活動における情報、知識及び技術等の共有化、二次災害防止を図ることを目的に開催された研修会に参加しました。
研修会では、津波・大規模風水害対策車、重機及び重機搬送車の説明や実働展示が行われ、その後、2ブースに分かれて土砂埋没救助訓練を実施しました。
土砂に埋没した要救助者の救助要領、土砂排出手順等を確認するとともに、消防本部間の連携強化を図りました。
参加した職員によるフィードバックを行い、様々な災害現場に対応できる知識、技術の向上に努めてまいります。
防火図画入選者の表彰式
市消防本部では、秋の全国火災予防運動にあわせ市内の小学4年生を対象に防火図画を募集し、26回目となる今年は、市内10小学校から176点の作品が寄せられました。
厳正な審査により、寄せられた作品の中から特選1点、入選3点、佳作6点を選出し、見事「特選」に輝いた市立久美浜小学校4年の安達 匠真(あだち たくま)さんに10月26日(水曜日)、廣野克巳消防長が同校を訪問し表彰状を贈呈するとともに、その栄誉を称えました。
消防本部では特選作品をもとに火災予防運動ポスターを制作し、完成したポスターを市内の事業所や学校などに配布して、市民に対し広く「火災予防」を呼びかけてまいります。
新人救急救命士の実技評価訓練を実施!
令和4年10月3日(月曜日)、新人救急救命士1名の実技評価訓練を実施しました。
この訓練は、救急隊の救急救命士として活動(観察、処置、特定行為等)するため、指導救急救命士から実技評価を受ける訓練です。
訓練では、「成人男性が自宅内で突然倒れた。」という想定のもと、チューブを用いた気道確保、静脈路確保(点滴)、薬剤投与などの救命処置を行いました。
「救命のリレー」で安全・安心なまちづくり ~救マーク認定証交付式を開催~
令和4年9月9日(金曜日)、救急医療週間(9月4日~10日)にあわせて、上級救命講習の修了者が常駐し、救急事故に速やかに対応できる「救マーク認定事業所」の認定交付式を行いました。
「救マーク認定事業所」とは、ショッピングセンターや宿泊施設など、多数の市民や観光客などが利用する事業所に、上級救命講習を修了した従業員が営業時間中に1名以上常駐し、施設内での救急事故に対する「救急活動計画書」に則って、救急車が現場に到着するまでの間、適切な応急手当を行うことで救命率の向上につなげることを目的とした制度です。
今年度、新規事業所として認定される1事業所の関係者に対し、廣野消防長から「認定証」と「救マークプレート」の交付が行われ、すでに交付済みの事業所とあわせて、市内の認定事業所は105事業所となりました。
救マーク認定事業所では、円滑な救急活動へのご協力の他、そばに居合わせた人(バイスタンダー)による適切な応急手当のおかげで、心肺停止の状態から社会復帰を果たされるなどの奏功例もあります。
市消防本部では、今後も積極的にこの制度の普及に努め、より多くの事業所の認定を目指し、さらなる応急手当の普及・啓発とともに救命のリレーの強化で、安全・安心なまちづくりに努めてまいります。
救急隊の知識・技術力向上を目指して!
市消防本部では救急医療週間中の9月6日、7日の二日間、救急隊としての知識と技術力の向上を目的に署内救急訓練を行いました。
訓練の想定は、胸痛、意識障害、呼吸困難、外傷、心肺停止の5パターンがあり、各救急隊は事前訓練を継続し、救急訓練に臨みました。
訓練後は検討会を行い、指導救命士から時間管理の徹底・プロトコールの理解を深める等、改善点やアドバイスを受け話し合いました。
消防本部では引き続き、救急隊員のレベルアップに力を入れ、傷病者の救命率向上や後遺症の軽減に努めてまいります。
令和4年度「京丹後市防災訓練」を実施!
・市消防本部による土砂埋没車両からの救出、救助訓練
・京丹後警察署による倒壊家屋からの救出、救助訓練
・市消防団による救出された要救助者の搬送訓練
・京都府警察航空隊による孤立地域からのホイスト救助訓練
・京都市消防航空隊による空中消火訓練
京都府消防操法大会に出場!
第28回京都府消防操法大会が8月28日(日曜日)、京都府立丹波自然運動公園で開催され、京丹後市を代表してポンプ車操法の部に「弥栄方面隊」、小型ポンプ操法の部に「丹後方面隊」が出場しました。
大会では、京都府下の消防団からポンプ車操法の部11隊、小型ポンプ操法の部11隊、計22隊が出場し、日頃の訓練により磨き上げた操法技術を競いました。
京丹後市消防団は、厳しい暑さの中で積み重ねてきた訓練の成果を発揮し、弥栄方面隊が準優勝と大健闘、丹後方面隊も上位に食い込む第5位という優秀な成績を収めました。
【京丹後市消防団の出場者】
ポンプ車操法の部:弥栄方面隊 小型ポンプ操法の部:丹後方面隊
指揮者 藤原 真平(部長) 指揮者 中江 将也(班長)
1番員 木下 剛志(団員) 1番員 蒲田 裕将(団員)
2番員 奥田 康平(団員) 2番員 畑中 景太(団員)
3番員 永嶋 直人(団員) 3番員 中村 龍哉(団員)
4番員 坪倉 大智(団員)
【大会結果】
ポンプ車操法の部 小型ポンプ操法の部
優 勝 京丹波町消防団 優 勝 京丹波町消防団
準優勝 京丹後市消防団 準優勝 精華町消防団
第3位 綾部市消防団 第3位 与謝野町消防団
京都府立峰山高等学校アニメーション部に感謝状を贈呈!
京丹後市消防本部では、令和4年8月22日(月曜日)、消防士募集ポスターを共同制作した京都府立峰山高等学校アニメーション部に対し、消防長から感謝状を贈呈しました。
これは、消防職員の募集について、新しい視点での広報を展開しようと消防士募集ポスターのデザインを同校に依頼したところ、制作にご協力いただいたものです。
女性消防士を基調としたデザインは、女性が消防士を職業として選択するきっかけとなるもので、イラスト調の柔らかい表現により、女性のみならず男性もが消防士をより身近に感じることができるポスターとなりました。
ポスターは、市内の公共施設や事業所に掲示しています。
令和4年度京丹後市職員採用試験案内(PDFファイル:818.9KB)
※申込期間:8月26日(金曜日)まで
FMたんご「Live119」ラジオ収録!
消防本部では、7月1日から運用を開始した「映像通報システムLive119」を広く市民やリスナーのみなさんに知っていただくため、NPO法人京丹後コミュニティ放送「FMたんご」さんにお邪魔して、~京丹後市消防本部「Live119」ラジオ寸劇~のラジオ収録を行いました。
言葉だけで伝える難しさを感じながらも、一緒にご出演いただいたパーソナリティさんにレクチャーしていただき、Live119について分かりやすくお伝えできる収録ができました!
放送時期は、8月中旬からを予定していますので、「FMたんご79.4MHz」にチャンネルを合わせてみてください!
■映像通報システム「Live119」
京丹後市消防本部[公式YouTubeチャンネル]
救急救命士養成課程への派遣職員が事前研修の成果を披露!
8月4日(木曜日)、今年度、京都市消防学校で行われる救急救命士養成課程に臨む職員が、事前研修の成果としてシミュレーション訓練を披露しました。
訓練は、家族(成人男性)が食事中に急に倒れたとの救急事案を想定し、傷病者に対して気管挿管による気道確保や点滴、薬剤投与など高度な救命処置を的確に行い、事前研修の成果を十分に披露しました。
職員は今月末から約半年間、年度末に行われる国家試験に向けて座学や訓練など厳しい研修に臨みます。
消防本部では引き続き、救急隊員のレベルアップに力を入れ、傷病者の救命率向上や後遺症の軽減、応急手当の普及に努めてまいります。
ケーブルテレビの収録を行いました!
消防本部は7月25日(月曜日)、市ケーブルテレビの特番「社会科見学TV」の収録を行いました。
「社会科見学TV」とは、コロナ禍で社会科見学の授業が減ってしまった小学生に向けた番組を作ってほしいという依頼からスタートした番組で、市内にある様々な施設が、どのような役割を担っているのかを大人も子供も分かりやすく、そして楽しく紹介する番組です。
日ごろ、災害現場で活動している雰囲気とはまったく違い、リポーターを務める市政策企画課の原田さんに引っ張っていただきながら、消防本部の仕事について、笑いあり、緊張ありの収録となりました。どのような番組に仕上がっているのか楽しみです。
放送時期は、8月下旬頃を予定していますので、乞うご期待!
移動消防学校を開催!
令和4年7月23日(土曜日)、市消防団では、8月28日(日曜日)に開催される京都府消防操法大会を前に、大会への出場隊員をはじめ消防団として消防操法の知識や技術を高めるため、京都府立消防学校の教官を講師としてお招きして、移動消防学校を開催しました。
大会まであと1か月。習得した知識、技術を訓練に生かし、大会本番では、京丹後市消防団らしい消防操法が展開できるように頑張ります!
令和4年度 甲種防火管理新規講習を行いました
6月23日(木曜日)、6月24日(金曜日)の2日間、アグリセンター大宮において甲種防火管理新規講習を行いました。
受講者数は59名で、講義や消火器の取り扱いなどの実技を通して防火管理者として必要な知識や心得について学んでいただきました。2日目の最後に行った効果測定の結果も良好で、受講者全員に修了証を交付しました。
今後、みなさんが各事業所で防火管理者としてご活躍されることを期待しています。
京都府消防救助選抜会に出場!
6月28日(火曜日)、京都市消防活動総合センターで京都府消防救助選抜会が開催され、消防本部から13名の隊員が「はしご登はん訓練」「ほふく救出訓練」「引揚救助訓練」の3種目に出場しました。
新型コロナウイルス感染症の影響で3年ぶりの開催となった選抜会は、当消防本部においては初めて出場する隊員も多く、少し緊張した面持ちではありましたが、それぞれに掲げた目標にチャレンジすることができ、一定の成果を収めることができました。
この訓練で培った知識や技術を、市民の安心・安全のため今後の業務に活かしていきます。
第10回京丹後市消防操法競技大会
第10回京丹後市消防操法競技大会が6月26日(日曜日)、京丹後市大宮自然運動公園で開催され、各方面隊からポンプ車操法の部6隊、小型ポンプ操法の部6隊の計12隊が出場し、訓練で培った操法技術とスピードを競いました。
なお、優勝隊は、京丹後市の代表として8月28日(日曜日)に京都府立丹波自然運動公園で開催される第28回京都府消防操法大会に出場します。
【結果】
ポンプ車操法の部 優秀操作員
優 勝 弥栄方面隊 指揮者 弥栄方面隊 藤原 真平(部長)
準優勝 峰山方面隊 1番員 弥栄方面隊 木下 剛志(団員)
第3位 久美浜方面隊 2番員 峰山方面隊 村岡 嵩平(団員)
3番員 久美浜方面隊 中田 大輔(団員)
4番員 久美浜方面隊 奥本 哲也(団員)
小型ポンプ操法の部 優秀操作員
優 勝 丹後方面隊 指揮者 丹後方面隊 中江 将也(班長)
準優勝 網野方面隊 1番員 大宮方面隊 堀 晋 弥(団員)
第3位 峰山方面隊 2番員 丹後方面隊 畑中 景太(団員)
3番員 網野方面隊 松尾 和貴(団員)
海開きを前に、官・民合同の水難救助訓練を実施!
海開きを目前に控えた6月23日(木曜日)、久美浜町の小天橋海水浴場でおこなわれた官・民合同の水難救助訓練に参加しました。
訓練は、「海水浴場で遊泳中の複数名が、強風により沖合に流された事故」を想定。事故を発見した監視員の118通報で訓練を開始し、参加機関が連携して要救助者を検索、救助しました。
検索要領や救助手順をしっかり確認し、海での事故に備えます。
※参加機関:舞鶴海上保安部、京丹後警察署、京都府水難救済会(久美浜救難所)、京丹後市消防本部
危険物施設 特別査察及び合同消防訓練を実施!
市消防本部は6月7日(火曜日)、危険物安全週間に伴い、大宮町森本地内「日本インパクト株式会社」において市内最大規模の「危険物屋内貯蔵所」の特別査察を実施しました。併せて、地震により貯蔵所内で発生した火災を想定した消防訓練を事業所と合同で行いました。
従業員が非常ベルの鳴動により貯蔵所内の火災を発見。通報を受けた市消防本部は指揮隊及び消防隊を出動させ、泡消火薬剤による消火活動を実施。貯蔵所内に取り残された一酸化炭素中毒疑いの傷病者を救出後、事業所敷地内にあるドクターヘリランデブーポイントへの搬送を行いました。
水難救助訓練を実施!
令和4年5月24日(火曜日)と25日(水曜日)の2日間にわたって、久美浜町の蒲井漁港で水難救助訓練を実施しました。
今回は夏の海水浴シーズンを見据えた基本訓練で、安全管理意識と基本動作の徹底を主眼に、ダイバー班とボート班が連携して訓練を行いました。
起きて欲しくない海の事故ですが、「もしもの事故」に備えて、消防本部では引き続き訓練に励みます。
令和4年度 署内消防救助選抜会を実施!
令和4年5月20日(金曜日)、京都府消防救助選抜会への派遣隊員を選考するため、署内消防救助選抜会を実施しました。
選抜会は、「はしご登はん」「ほふく救出」「引揚救助」の3種目に分かれて行い、18人の隊員が日頃の訓練の成果を発揮しました。
選考の結果選ばれた隊員は、6月28日(火曜日)に京都市消防活動総合センターで開催される京都府消防救助選抜会に出場します。
峰山消防署で新しい消防ポンプ自動車の運用を開始
~車両配備式を開催~
3月9日(水曜日)、更新となる車両(本署のポンプ車【P22】)の配備式を行いました。
更新車両は、CAFS(キャフス/Compressed Air Foam System)装置を搭載した車両で、600Lの水を積載しています。
CAFSとは、水に少量の消火薬剤を加え、そこに圧縮空気を送り込むことにより発泡させるシステムのことです。ホースラインを変えずに水・泡・混合液の放射切り替えが可能で、状況に応じた消火活動を素早く行えます。CAFS装置を活用することで、少ない水で効率よく消火することができます。
京丹後市消防団 消防車両2台を更新!
~車両配備式を開催~
2月13日(日曜日)、市消防団に配備している消防車両2台を更新し、新たに配備される多機能型消防ポンプ自動車の配備式を開催しました。
式典は、中山市長のあいさつ、川浪団長の訓示にはじまり、引き続いて、業者による車両・救助資機材の取り扱い説明が行われました。
多機能型消防ポンプ自動車は、高性能なポンプによる放水が可能なほか、チェンソーやエンジンカッターなど救助活動をサポートする資機材を積載しており、自然災害等における救助現場での活躍も期待されます。最新の機能性を誇る新車両を目の前にして、団員も地域住民の安心・安全への思いを新たにしました。
また、今回役目を終える車両は、いずれも20年以上を経過しており、長きにわたる活躍に対して、参加者から感謝と労いの言葉がかけられました。
市消防団として、新たに配備される車両と共に、より一層の火災予防への取り組みを進めてまいります。
令和4年消防出初式
「火災ゼロ」への願いを込めて
1月9日(日曜日)、「火災ゼロ」への願いを込めて、「京丹後市消防出初式」を京都府丹後文化会館ホールで開催しました。
式典では、中山市長より式辞、池田消防長、川浪団長より身の引き締まる訓示を受け、令和3年において優良な功績を収められた168名の消防団員に対して表彰を行いました。また、本田太郎衆議院議員をはじめご来賓の方々のご臨席を賜り、出初式の開催にあたってのご祝辞をいただきました。
屋外式典では、天候にも恵まれ多くの見学者が見守る中、消防職員、消防団員並びに消防車両による市中行進や、一斉放水を披露しました。
令和4年の年頭に、「市民の安心・安全」「火災のない街、京丹後」への決意を新たにしました。
消防出初式
~「火災ゼロ」への願いを込めて~ “消防出初式”を開催します!
日時 令和4年1月9日(日曜日) 午前9時30分開式
会場 京都府丹後文化会館ホール(京丹後市峰山町杉谷)
内容 式典(優良消防団員表彰など)
市中行進・一斉放水(荒天の場合は中止)
※新型コロナ感染症対策を実施したうえで開催します。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
京丹後市消防本部 峰山消防署
〒627-0011
京都府京丹後市峰山町丹波826番地の1
電話番号:0772-62-0119(代表) ファックス:0772-62-6119
お問い合わせフォーム
更新日:2022年12月21日