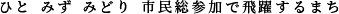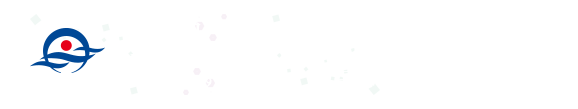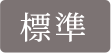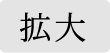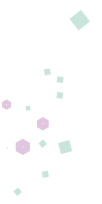アルコール
お酒は楽しくおいしく健康に
「酒は百薬の長」といわれるように、適度な量なら血行をよくしたり、リラックス効果があります。ただ、過度のお酒はアルコール依存症や肝機能障害を招く原因になり、大変危険です。また飲みすぎは、カロリーのとりすぎになるのと同時に、食欲亢進作用があるため肥満を誘引します。
過度のアルコールが及ぼす健康障害
- 肥満→動脈硬化
- 昏睡(急性アルコール中毒)
- 胃・十二指腸潰瘍
- 脂肪肝→肝硬変→肝がん
- 膵炎
- 痛風
- 高血圧
- アルコール依存症→手足の震え・幻覚→認知症
飲んだお酒は体の中でどうなるの?
- 口から入ったアルコールは胃から約20%、小腸から約80%が吸収されます。そして血液に入って数分のうちに全身にくまなくしみわたります。
- 体内に入ったアルコールの大部分が肝臓で代謝されます。肝臓ではアルコールはアセトアルデヒドを経てアセテート(酢酸)に分解されます。
- アセテート(酢酸)は血液によって全身をめぐり、筋肉や脂肪組織などで水と二酸化炭素に分解されて体外に排出されます。
- 摂取されたアルコールの2~10%が、そのままのかたちで尿・汗・呼気から排泄されます。
<社団法人アルコール健康医学協会より>
肝臓とアルコールの関係

お酒に含まれるアルコールを処理する臓器は肝臓ということは皆さんよくご存知だと思います。では、アルコール処理にかかる時間はどのくらいでしょうか?体重により処理能力には差がありますが、ビール中びん3本で8~10時間もかかり、仮に深夜までお酒をのんでいた場合、翌朝もアルコールが残っていることになります。
また、毎日過度の飲酒を続けた場合、脂肪肝から肝硬変、肝がんになる可能性もあります。
肝臓はアルコール処理だけでなく、様々な栄養素の代謝も行っており、大量のアルコールは肝臓に負担をかけることになります。肝臓は「沈黙の臓器」といわれるように、少々のことではねをあげませんので自覚症状がないまま病気が進行していきます。まずは血液中のγ-GTP値が上がってきたら脂肪肝を疑い注意が必要です。週に2日は休肝日を設け、適度な飲酒を心がけましょう。
お酒の上手な飲み方
お酒の適量:飲酒量には個人差がありますが、適正なアルコール量は一日約20グラム程度とされています。
お酒の適量とエネルギーの目安

ワインならグラス2杯(175キロカロリー)

ウイスキーならダブル1杯(165キロカロリー)

焼酎(25度)なら2/3合(175キロカロリー)

ビールなら中ビン1本分(200キロカロリー)

日本酒なら1合(196キロカロリー)
適正飲酒の10か条
- 談笑し 楽しく飲むのが基本です
- 食べながら 適量範囲でゆっくりと
- 強い酒 薄めて飲むのがオススメです
- つくろうよ 週に二日は休肝日
- やめようよ きりなく長い飲み続け
- 許さない 他人(ひと)への無理強い・イッキ飲み
- アルコール 薬と一緒は危険です
- 飲まないで 妊娠中と授乳期は
- 飲酒後の運動・入浴 要注意
- 肝臓など 定期検査を忘れずに
<社団法人アルコール健康医学協会より>
お酒は20歳になってから
未成年者は、アルコールを分解する仕組みが未熟で、急性アルコール中毒になりやすく命の危険にさらされされます。また、成長発達の著しい時期のアルコールは、性ホルモンへの影響や、脳の発達障害など様々な悪い影響を及ぼします。
親戚の集まり等で安易に子どもにすすめないように、周りの大人が注意してあげましょう。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康長寿福祉部 健康推進課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0350 ファックス:0772-62-1156
お問い合わせフォーム
更新日:2018年03月27日