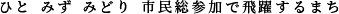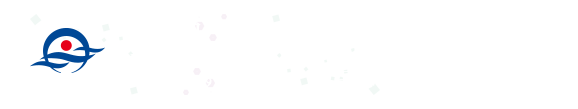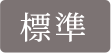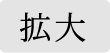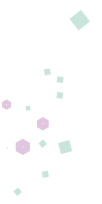慢性腎臓病(CKD)の重症化を防ごう!
慢性腎臓病(CKD)とは、「腎障害」か「腎機能低下」のいずれか、あるいは両方が3カ月以上以上続く状態のことです。現在、慢性腎臓病の患者数は1,330 万人を超え、成人の約8人に1人に当たる数となっています。市の検診結果では60 歳代から、要医療・要指導判定の方が増えています。 ※検診結果票の「腎機能」欄で、クレアチニンと尿タンパク、eGFRを確認してください。
慢性腎臓病の定義

慢性腎臓病(CKD)重症度分類
1.尿検査や血液検査、画像検査などで、腎臓に明らかな障害が認められる。特に尿タンパク(もしくは尿中アルブミン)が出ていることが重要。
2.腎臓のろ過機能が健康な人の60%未満に低下。
→1.と2.のいずれか、あるいは両方が3カ月以上続く状態。
慢性腎臓病は自覚症状がありません

慢性腎臓病は、初期の自覚症状がほとんどありません。むくみ、だるさ、貧血、吐き気、食欲不振などの症状が現れたときには、すでに病気が進行していることがほとんどです。
| 腎臓は一度機能が低下すると、元に戻りにくい臓器です。放置すると末期腎不全に陥り、人工透析が必要になります。それだけでなく、脳卒中や心筋梗塞などの発症リスクを高めます。 |
生活習慣を見直し、慢性腎臓病を予防!
食生活の改善と運動で肥満を解消し、高血糖や高血圧にならないことが大切です。また、喫煙は慢性腎臓病を悪化させます。ぜひ禁煙に取り組みましょう。
食生活改善のポイントは2つ
Point1.減塩
1日の食塩摂取量は、男性8グラム未満、女性7グラム未満、高血圧の方は6グラム未満!
Point2.エネルギーの取り過ぎ注意
主食・主菜・副菜をバランスよく食べる!
減塩のポイント

1.薄味に慣れる
昆布やかつお節、煮干しの旨味を生かしただしをとる。新鮮な旬の食材を利用する。
2.漬物、汁物は少なめに
塩分の多い漬物や汁物を食べる回数と量を減らす。
3.効果的に塩味を使う
かけて食べるより、つけて食べるほうが食塩の摂取が少なくてすむ。
4.塩味の代わりになる食材
レモンなどのかんきつ類や酢などの酸味、香辛料やハーブなどの辛味や香味を利用。揚げ物や炒め物で油のうま味を利用する。
5.練り製品・加工食品・酒のさかなに注意
6.食べ過ぎに注意
せっかくの薄味料理も食べ過ぎると
塩分の量が多くなる。
早めの対策を!
腎臓は、体全体の健康を左右する重要な臓器です。重症化を予防するためには、早期発見・早期治療によって、腎臓の機能を低下させないことが重要です。定期的に検診を受けて腎臓の状態を確認したり、生活習慣を改善したりすることが大切です。
検診で異常が見つかった場合は、早めにかかりつけ医を受診しましょう。治療が必要な場合は、かかりつけ医から腎臓専門医を紹介するなど連携して治療をします。
また、食事や運動のことで相談をしたい方は、毎月第4月曜日に健康相談・栄養相談を行っていますので、ぜひご利用ください。相談日以外でも相談に応じますので気軽に、健康推進課へお問い合わせください。

年代別eGFR判定と平均値
京丹後市の状況(H30年度総合検診結果より)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康長寿福祉部 健康推進課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0350 ファックス:0772-62-1156
お問い合わせフォーム
更新日:2019年01月30日