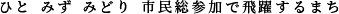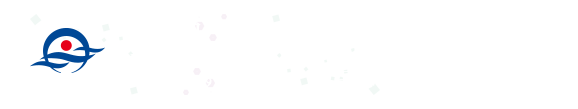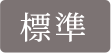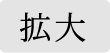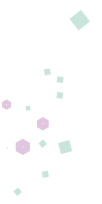障害(児)福祉サービス
児童福祉法に基づくサービスで、療育等の支援を必要とするお子さまが、下記のサービスを利用するための事業です。(京丹後市に居住地を有する児童が対象です。)
対象となる児童
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)のため通所による療育等の支援が必要なお子さまが対象です。
※障害者手帳等お持ちでない方については、支援の必要性について聞き取り調査を行います。
サービスの種類
| 給付の種類 | サービスの内容 |
|---|---|
| 児童発達支援 | 概ね、就学前の児童が対象となり、日常生活における基本的な動作の指導や知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行う。 |
| 放課後等デイサービス | 授業の終了後または休校日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力向上のための必要な訓練、社会との交流促進などの支援を行う。 |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を行う。 |
| 保育所等訪問支援 | 保育所、乳児院・児童養護施設等を訪問し、対象児童に対して、他児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを行う。 |
サービス利用開始までの流れ
1.相談
| 就学前(0歳~6歳) | 子育て支援課の保健師または障害者福祉課、各障害児相談支援事業所へ相談 |
| 就学後(6歳~18歳) | 障害者福祉課または、各障害児相談支援事業所へ相談 |
2.体験・見学
障害児通所支援事業所はあらかじめ、見学や体験することができます。
※障害児相談支援事業所、子育て支援課、障害者福祉課へご相談ください。
3.申請
障害者福祉課の窓口で申請してください。※申請者は利用を希望する「保護者」になります。
<申請に必要なもの>
1.申請者と申請児童のマイナンバーが確認できるもの。
・マイナンバーカード
・マイナンバーが記載された住民票
・マイナンバー通知カード
2.手続きに来られる方の本人確認ができるもの。
・顔写真付きの証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
3.お子さまの障害者手帳(※お持ちの方のみ)
・身体障害者手帳
・療育手帳
・精神保健福祉手帳
4.聞き取り調査
通所給付決定時に実施しなければならない調査があり、保健師がお子さまの近況や日常生活の様子など聞き取らせていただき、利用決定をする際の参考にさせていただきます。
(調査方法は、電話での聞き取りや、面談、訪問となります。)
5.サービス等利用計画(案)・障害児支援利用計画(案)の作成
障害児相談支援事業所の相談支援専門員が面談をして、通所時の計画(案)を作成します。
※セルフプラン(保護者が計画を作成する)での利用となる事業所もあります。その際は、申請時にセルフプラン(案)の提出が必要です。
6.支給決定・受給者証の交付
申請内容を確認し、市が支給決定し、通所受給者証を申請者へ交付します。
7.サービスの利用開始
交付された通所受給者証を事業者へ提示し、利用契約を行います。
その後、サービスの利用が開始できます。
8.更新手続きなど
サービスの利用開始月を基準に1年間の期限を設けています。
※期限が近づきましたら市から更新手続き案内を送付します。
※通所する事業所、氏名、住所、利用日数等、申請時から変更あれば、別途手続きが必要です。
サービス利用時の費用
(1)利用者負担上限額
下の表のとおり、世帯所得に応じて、1か月に負担する上限額が決められています。
| 区分 | 対象となる人 | 月額上限額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受給しているかた | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯のかた | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税所得割が28万円未満の世帯 | 4,600円 |
| 一般2 | 市町村民税課税世帯で「一般1」に該当しない世帯 | 37,200円 |
- 上記を判断する際の「世帯」の範囲は、『保護者の属する住民票上の世帯全員』です。
- 同じ世帯で、他にも障害児福祉サービスを受けているお子さまがいればその合算額が上限額を超えないように管理することができます。
(2)利用者負担上限月額管理について(複数の事業所・兄弟姉妹で利用する場合)
複数の障害児通所支援事業を利用し、利用者負担額が上限月額を超えることが予想される場合は、利用する事業所に上限月額の管理を依頼することができます。
また、障害のある兄弟姉妹が同じ事業所、それぞれ別の通所支援事業所を利用する場合も上限月額の管理を依頼することができます。
※利用者負担上限月額が0円の方は、上限月額の管理を依頼する必要はありません。
(3)就学前児童の利用者負担額の無償化について
下記の期間においては、児童発達支援(居宅訪問型を含む)・保育所等訪問支援の利用者負担額が無料です。
<対象となる期間>
満3歳になって初めての4月から小学校入学までの3年間
※医療費や食費等の実費分については、自己負担となります。
(4)多子軽減措置について
児童発達支援(居宅訪問型を含む)・保育所等訪問支援の利用者で以下の要件のいずれかに該当する場合、障害児通所支援の利用者負担額が軽減されます。
(ア)同一世帯に保育所等に通所している就学前の兄、または姉がいる場合。
(イ)世帯の市民税所得割の合計額が77,101円未満であり、通所決定保護者と生計を同じくする兄、または姉がいる。
【軽減後の費用】
第2子の場合・・・サービスに係る総費用学の100分の5
第3子の場合・・・無料
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康長寿福祉部 障害者福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0320 ファックス:0772-62-1156
お問い合わせフォーム
更新日:2025年08月18日