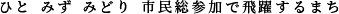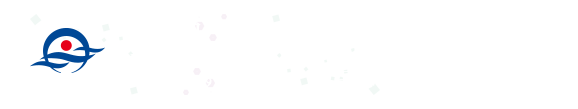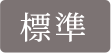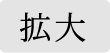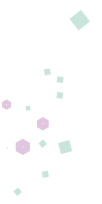国民年金の制度について
国民年金とは
国民年金は、すべてのかたに生涯にわたって基礎年金を支給する制度です。高齢や不慮の事故などによって、私たちの生活が損なわれることのないように、前もってみんなで保険料を出し合い、経済的にお互いを支え合う制度です。
基礎年金をベースに2階建の年金体系
日本の年金制度は、20歳以上の学生、自営業や会社員とその配偶者など、すべてのかたを加入対象として共通の基礎年金を支給する「国民年金」と、会社員や公務員などを加入対象として、基礎年金に上乗せして報酬比例の年金を支給する「厚生年金」などで構成されています。
国民年金では、老齢になったら老齢基礎年金、障害者になったら障害基礎年金、また生計を維持しているかたが死亡したときは遺族基礎年金が支給されます。
また、厚生年金加入であれば、老齢厚生年金・障害厚生年金・遺族厚生年金が上乗せされます。
国民年金に必ず加入するかた
国民年金に必ず加入する方
| 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | 第3号被保険者 | |
| 対象となる方 | 日本に住所のある農林漁業、自営業、学生、無職などのかた (20歳以上60歳未満) |
厚生年金保険や、共済組合等に加入している人 (原則として65歳未満) 届出をしなくても国民年金に加入したことになります。 |
厚生年金保険や、共済組合等に加入している第2号被保険者に扶養されている配偶者 (20歳以上60歳未満) |
| 届出 | 第1号被保険者に該当したときは、届出が必要です。 届出先:各市民局窓口、保険事業課 |
届出は勤務先が行いますので、本人が届出する必要はありません。 | 第3号被保険者に関する届出は、配偶者(第2号被保険者)の勤務先が行います。 |
| 保険料 | 保険料は、納付書や口座振替を利用して自分で納めます。 | 保険料は、給料から天引きされます。 | 保険料は、厚生年金の制度全体で負担されています。 個人で個別に納付する必要はありません。 |
年金手帳と基礎年金番号
国民年金や厚生年金に加入をしたかたには、年金手帳が交付されます。(令和4年4月1日からは手帳が廃止され、この日以降に加入をしたかたには「基礎年金番号通知書」が送付されています。)この年金手帳は、加入制度が変わったときや、年金の請求手続きなど一生をとおして使用しますので、大切に保管してください。
なお、年金手帳は、平成9年1月から「基礎年金番号」が印字された青色の表紙のものです。それ以前のオレンジ色の年金手帳や、「厚生年金保険被保険者証」、茶色の「国民年金手帳」も引続き使用できます。 基礎年金番号は、共済組合も含めて、加入する年金制度が変わっても、一人のかたが一生を通して使用する番号です。
届出をお忘れなく!こんなときこんな手続きを
資格関係
| こんなとき | 必要な手続き | 手続きをする場所 |
| 会社を退職したとき (厚生年金の資格喪失) |
国民年金の加入手続きをする | 第1号被保険者:各市民局窓口、保険事業課 |
| 被扶養者でなくなったとき (第3号から第1号へ) |
第1号被保険者の該当手続きをする | 第1号被保険者:各市民局窓口、保険事業課 |
| 配偶者が退職したとき (第3号から第1号へ) |
第1号被保険者の該当手続きをする | 第1号被保険者:各市民局窓口、保険事業課 |
| 海外に居住するとき | 資格喪失の手続き | 第1号被保険者:各市民局窓口、保険事業課 |
| 海外に居住するとき | 任意加入の手続き | 各市民局窓口、保険事業課 |
保険料関係
| こんなとき | 必要な手続き | 手続きをする場所 |
| 納付書をなくした | 納付書の再発行手続きをする | 舞鶴年金事務所 |
| 保険料を口座振替で納付したい | 口座振替の手続きをする | 金融機関・舞鶴年金事務所 |
お手続きには基礎年金番号のわかるもの(年金手帳など)をお持ちください。
国民年金の保険料は?
令和7年度(令和7年4月~令和8年3月まで)の国民年金の保険料は、
第1号被保険者のかた
- 定額保険料 1ヶ月 17,510円
- 付加保険料 1ヶ月 400円
将来受給する年金は、付加保険料支払月数×200円が上乗せされます。
この他、国民年金に上乗せする年金として、国民年金基金があります。
(国民年金基金に加入した人は、付加保険料を納めることはできません。)
詳しくは、 下記の「国民年金基金のホームぺージ」をご覧ください。
- 保険料の納付には前納の制度があります。
- 口座振替の手続きは、金融機関・郵便局でお願いします。
- 納付書での納付は、金融機関・郵便局・コンビニでできます。
- クレジットカードでのお支払ができるようになりました。
- 令和5年2月20日(月曜日)からスマートフォンアプリを利用した電子決済(スマホ決済)が導入されました。
納付方法など、詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
保険料を納めることが困難なとき
保険料の納付が困難なときは、次の制度があります。
保険事業課(電話:0772-69-0220)及び各市民局窓口でご相談ください。
法定免除
次に該当する方は、保険料の納付が免除されます。
- 生活保護法による生活扶助を受けているかた
- 障害基礎年金または厚生年金の障害年金(1・2級)の受給権のあるかた
- 厚生労働大臣が指定する施設(ハンセン病療養所、国立保養所など)に入所している
申請免除
経済的な理由で保険料の納付が困難なかたは、免除申請をされると、所得の状況等に応じて保険料の「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」の納付免除が承認されます。
納付猶予制度
50歳未満で学生以外の方の納付猶予制度です。
申請免除は、家族と同居の場合、本人の所得が少なくても世帯主の所得が多ければ免除が承認されません。
納付猶予制度は、50歳未満の方で、本人及びその配偶者各々の所得が一定額以下の場合に保険料の納付を猶予する制度です。
平成27年度まで30歳未満が対象だった「若年者納付猶予制度」が、平成28年度より50歳未満まで拡充されました。
学生納付特例制度
在学期間中の国民年金の保険料納付を猶予する制度です。
大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校及びその他の教育施設に在学中で、学生本人の所得が一定額以下であるかたの保険料の納付を猶予する制度です。
申請手続きについて
- 免除等が申請できる期間は、過去期間は申請書が受理された月から2年1ヶ月前(納付済の月を除く)まで、将来期間は翌年6月(1月~6月に申請するときはその年の6月)までです。
- すでに納付済みの期間は免除申請できません。
- 所得を申告していない方は、所得の申告を済ませてください。
- 全額免除あるいは納付猶予が承認された場合、免除の継続申請ができます。継続申請を希望されるかたは、申請されるときにお申出ください。
保険料を未納のまま放置すると、将来の老齢基礎年金やいざというときの障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取ることができない場合があります。保険料を納めることが困難なときは、必ず、ご相談ください。
産前産後期間にかかる国民年金保険料の免除申請について
産前産後の国民年金保険料免除制度は、次世代育成支援の観点から国民年金第1号被保険者が出産をされた際、産前産後の国民年金保険料が一定期間免除される制度です。なお産前産後期間の保険料を前納している場合には、保険料の全額が還付(返金)されます。
※国民年金第1号被保険者とは…20歳以降60歳未満の自営業者・農林漁業者とその家族、学生、無職のかたを指します。
保険料納付が免除される期間は次のとおりです。
- 出産予定日または、出産日が属する月の前月から4ヵ月間
- 多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヵ月前から最大6ヵ月間
※出産とは、妊娠85日(4ヵ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
20歳になったとき
・20歳以上60歳未満の学生・農林漁業者・自営業者・無職の方等(国民年金第1号被保険者)は国民年金に加入することが義務付けられています。
・20歳になった方には、日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」や納付書等により、国民年金に加入したことをお知らせします。
・公的年金制度は、老後や障害を負ったときに、働いている世代みんなで支えようと考えて作られた仕組みです。
・若いときに公的年金制度に加入して、保険料を納め続けることで、老後や、病気やケガで障害が残ったとき、家族の働き手が亡くなったときに、年金を受け取ることができます。
詳しい動画は下記のリンクから
国民年金を請求(裁定請求)するとき
国民年金の請求
| 裁定請求する年金の種別 | 届出先 |
| 老齢基礎年金 :第1号被保険者期間のみの場合 | 各市民局窓口、保険事業課 |
| 老齢基礎・厚生年金:過去に第2号、第3号被保険者期間があるとき | 舞鶴年金事務所 |
| 障害基礎年金 :第1号被保険者期間内に初診日のある場合 | 各市民局窓口、保険事業課 |
| 障害基礎・厚生年金:第2号、第3号被保険者期間内に初診日がある場合 | 舞鶴年金事務所 |
| 遺族基礎年金 :第1号被保険者であるとき亡くなった場合 | 各市民局窓口、保険事業課 |
| 遺族基礎・厚生年金:第2号、第3号被保険者であるとき亡くなった場合 | 舞鶴年金事務所 |
年金を受給されているかたの主な手続き
年金受給の主な手続きについて
| こんなとき | 届出書類 | 提出時期 | 提出先 |
| 年金の受取り金融機関を変える | 受取機関変更届 | その都度 | 舞鶴年金事務所、金融機関 |
| 年金を受けているかたが亡くなったとき | 死亡届・未支給請求書 | 死亡から14日以内 | 舞鶴年金事務所、各市民局窓口、保険事業課 |
| 二つ以上の年金が受けられるようになった | 年金受給選択申出書 | 受けられるようになったとき | 舞鶴年金事務所、各市民局窓口、保険事業課 |
届出・請求受付窓口
保険事業課(峰山庁舎1階)
各市民局窓口
- 大宮市民局
- 網野市民局
- 丹後市民局
- 弥栄市民局
- 久美浜市民局
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民環境部 保険事業課
〒627-8567
京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0220 ファックス:0772-69-0901
お問い合わせフォーム
更新日:2020年04月01日