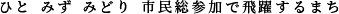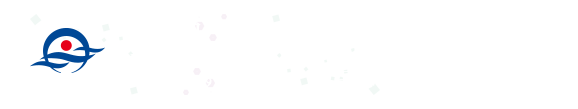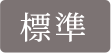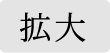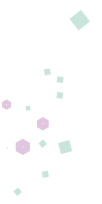児童手当制度

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育している方に支給されるものです。
児童手当は、令和6年10月分から制度が改正されています。制度改正の内容については、こちらをご確認ください。
1.制度の概要
(1)支給対象
高校生年代まで(18歳に到達後の最初の年度末まで)の日本国内に住所を有する児童
※原則として、児童が日本国内に居住している場合に支給されます。(留学中は除く)
(2)受給資格者 ※従来の所得制限は撤廃
対象児童の監護・生計要件を満たす父母等
- 両親が別居している場合も、生計維持者(主に所得の高い方)が手当の受給者となります。(離婚協議中で父母別居の場合、児童と同居している方に支給する場合があります。)
未成年後見人や父母指定者に対して、父母と同様の要件で手当を支給します。
- 未成年後見人や父母指定者(父母が国外に居住している場合に、父母などが指定した方)についても、父母と同様の要件で手当が支給されます。
里親、児童福祉施設などへの支給
- 児童が里親などに委託されている場合や施設に入所している場合は、原則として、その児童の里親などや施設の設置者に支給します。
(3)支給手当額
|
児童の年齢 |
児童手当の額(1人あたり月額) |
|
|
第1子・2子 |
第3子以降(※1) |
|
|
3歳未満 |
15,000円 |
30,000円 |
|
3歳から高校生年代 |
10,000円 |
|
(※1)多子の数え方は、受給者が監護・養育等をしている0歳から22歳の到達後の最初の年度末までの間にある子のうち、年長者から第1子、第2子、第3子以降と数えます。
多子算定例
| 年齢 | 実際の順番 | 多子算定の順番 | 支給額 |
| お子様A:24歳 | 第1子 | 算定外(22歳年度末以降) | 支給なし |
| お子様B:19歳 | 第2子 |
養育している場合は、第1子 ※確認書の提出が必要 |
支給なし ※多子算定可 |
| お子様C:16歳 | 第3子 | 第2子 | 10,000円 |
| お子様D:14歳 | 第4子 | 第3子 |
30,000円 ※多子加算あり |
| 支給額計 | 40,000円 | ||
(4)支給時期
- 原則として、年6回(偶数月:2月、4月、6月、8月、10月、12月)の10日に、各前月までの2カ月分を支給します。※当日が土日祝の場合は、その直前の金融機関営業日に支給します。
- 手当は、原則として請求した日の属する月の翌月分から支給します。ただし、出生日や前住所の転出予定日等が月末に近い場合、請求日が翌月になっても事実発生日の翌日から起算して15日以内であれば、請求した月分から支給します。
2.手当の支給を受けようとするとき
児童手当を受けるためには、請求手続きが必要です。
認定請求(新規申請) [オンライン対応可]
手当を受けるためには「認定請求書」の提出が必要です。
- 児童が生まれたとき
- 受給者が他の市町村から転入したとき
- 児童を養育するようになったとき(離婚、再婚、施設退所など)
- 受給者が公務員でなくなったとき
※里帰り出産などで、母親が一時的に現住所を離れている場合も、現住所地の市町村への申請をお忘れなく!
※請求手続きが遅れると、手当を受給できない月が発生することがあります。
※公務員の方は勤務先での申請となります。
<必要な添付書類>
- 請求者本人の健康保険証、資格証明書などの写し、または提示
- 請求者名義の金融機関の通帳、またはキャッシュカード等の写し
- 請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 児童が市外在住の場合は、児童の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
※ 他にも個別の状況に応じて必要な書類がありますのでお問い合わせください。
次の事由が発生したときは「額改定認定請求書(額改定届)」の提出が必要です。
- 児童手当を受給中で、第2子以降の出生等により養育する児童が増えたとき
- 監護相当・生計費の負担をしなくなった等により、養育する児童の数が減ったとき
額改定認定請求書(額改定届)(PDFファイル:205.3KB)
額改定認定請求書(額改定届):記入例(PDFファイル:358KB)
※第3子以降の加算対象者は、同居・別居にかかわらず22歳到達後の年度末までに監護相当・生計費の負担の有無が変わった場合も手続きが必要です。
<必要な添付書類>
- 請求者本人の健康保険証、資格証明書などの写し、または提示
- 児童が市外在住の場合は、児童の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
※他にも個別の状況によって必要な書類がありますのでお問い合わせください。
現況届について
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監護や保護、生計同一関係など)を確認するためのものです。届け出が必要な方には個別にご案内します。
現況届の提出が必要な方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 進学以外の就職等をする子を多子加算の要件児童として申告している方
- その他、本市から提出案内があった方
※現況届の提出がない場合は、当該年度の6月分以降の手当が受けられなくなります。
3.手当の支給が終わるとき
手当の受給要件を満たさなくなったときは「受給事由消滅届」の提出が必要です。手当の支給は、支給事由の消滅した日の属する月で終了します。[オンライン対応可]
手当の受給資格がないにもかかわらず、届出を行なわずに手当を受給した場合は、受給された金額を返納していただくことになりますので、手続きの必要な方は速やかに届出してください。
児童手当の受給消滅事由
- 児童を養育しなくなったとき(離婚、施設入所、拘禁など)
- 受給者がお亡くなりになったとき(※1)
- 受給者が京丹後市外に転出したとき(※2)
- 受給者が公務員になったとき(※3)
※1 支払うべき手当に未払いがあるときは、児童に未払い分の手当を支給します。「未支払 児童手当 請求書」を提出してください。(対象児童名義の通帳の写しが必要:複数の場合は年長者分)以降、新たに受給者となる養育者は、認定請求手続き(新規申請)が必要です。
※2 市外転出する場合で、引き続き手当の受給条件に該当するときは、転出予定日の翌日から起算して15日以内に転出先の市町村で手当の請求手続きをしてください。
※3 受給者が公務員になった場合は、届け出後に勤務先に認定請求(新規)してください。
4.その他、手続が必要なとき
次の事由に該当するときは、速やかに手続してください。
- 養育している児童の住所が変わったとき:「氏名住所変更届」
- 振込口座や口座名義を変更するとき:「金融機関変更届」
- 受給者、配偶者、市外居住の児童のマイナンバーが変わったとき:「個人番号変更等申出書」
- 離婚等により、配偶者を削除するとき:「個人番号変更等申出書」
- 婚姻等により、配偶者を登録するとき:「個人番号変更等申出書」
※手続きによって各種添付書類が必要となりますのでお問い合わせください。
5.個人番号(マイナンバー)の記載について
児童手当の手続き時には、必ず個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。
| 手続き内容 |
個人番号(マイナンバー)が必要な方 |
|---|---|
| 新たに児童手当を受給するとき「認定請求書」 | 請求者、配偶者 |
| 京丹後市外に居住している児童がいるとき「別居監護申立書」 | 市外に居住している児童 |
| 多子カウント(第3子以降)のための「監護相当・生計費の負担についての確認書」 | 監護に相当する世話をし、生計費の負担の対象となっている大学生年代の兄姉等 |
| 受給者、配偶者、市外に居住している児童のうち個人番号(マイナンバー)に変更があったとき「個人番号変更等申出書」 | 受給者、配偶者、市外に居住している児童及び大学年代の兄姉等 |
6.オンライン申請
7.寄付について
受給者は、次代を担う地域の児童の健やかな成長を支援するため、あらかじめ本市に申し出て、児童手当の全部または一部を簡便な手続きで寄付することができます。関心のある方は、こども未来課にお問い合わせください。
8.時効について
手当を受給する権利は、権利を行使できるとき(※1)から2年を経過したときに時効により消滅します。
※1(例)現況届を提出しなかったことにより、8月10日の定期支給を受けられなかった場合は、支払日の翌日(8月11日)が権利を行使できるときとなります。
9.手続き窓口
お近くの市民局またはこども未来課(峰山総合福祉センター東館)
電話番号:0772-69-0340
10.児童手当Q&A
Q1 監護相当の有無とは何ですか?
A1: 監護とは、お子さんの生活に必要とされる監督、保護を行うことを言います。通常、保護者として養育している場合は「有」に〇をつけます。「無」に〇をつけた場合は、児童手当の支給要件を満たさないため、手当の認定が受けられません。
Q2 受給者と児童が別居となった場合も手続きがいりますか?
A2:「氏名住所変更届」と「別居監護申立書」の提出が必要となります。オンライン申請、または窓口へお越しください。
※対象児童が京丹後市外で別居する場合は、児童の個人番号(マイナンバー)が必要になりますので、確認できるものをご用意ください。
Q3 指定の振込口座を子どもの名義のものにしたいです。
A3:振込口座は受給者ご本人名義の口座に限り、指定ができます。配偶者やお子さん名義の口座には変更できません。
Q4 受給者を配偶者に変更したいです。
A4:児童手当は、生計維持者(主に所得が高い方)が受給者になります。所得が同程度の場合は、お子さんをどちらが扶養しているか、どちらの健康保険に加入しているかなどを総合的に勘案して決定しています。
※ご事情がある場合は、こども未来課へご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
こども部 こども未来課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(峰山総合福祉センター)
電話番号:0772-69-0340 ファックス:0772‐62‐1156
お問い合わせフォーム
更新日:2025年02月20日