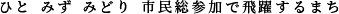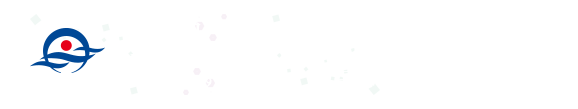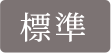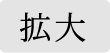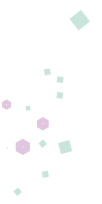「京丹後市認知症とともに生きるまちづくり条例」を制定しました
この条例は、認知症とともに生きるまちづくりの基本理念を定め、全ての市民が認知症の「ある」「なし」にかかわらず、安心していきいきと暮らすことができる地域共生社会の実現に寄与することを目的に制定しました。
この条例をきっかけに、誰もが認知症を自分事として捉え、認知症とともに歩むまちとして一丸となって取り組んでいきたいと考えています。
前文
急速な高齢化社会の進展に伴い、認知症の人の数が増加してきており、今後もその数は増加していくことが予測されています。また、認知症は、65歳未満で発症する若年性認知症もあり、誰もがなり得る身近な病気となっています。
認知症になったとしても、意思や感情は備わっており、「すべてのことを忘れる」、「何もできなくなる」といったものではありません。また、認知症は、早期診断・早期治療によって、その治療効果が期待できるとされています。
市では、これまで認知症に関する正しい理解と知識の普及啓発をはじめ、様々な認知症施策を推進してきました。また、本市は、人口に占める100歳以上の割合が全国平均、京都府平均に比べ極めて高い長寿のまちの特色を強みとして活かして、百歳になっても様々な分野において生涯現役で元気に活躍できる「百才活力社会」の実現に向けた取組を推進しています。
京丹後市まちづくり基本条例で掲げる「誰もが幸福をますます実感できる市民総幸福のまちづくり」を進めていく上で、「誰ひとり置き去りにされないまち」を実現していくことは、とても重要な課題です。その上で、誰が認知症になったとしても、住み慣れた地域でともに支え合いながら、安心して暮らすことのできる地域を実現していくことが重要で欠かせません。このためには、市、市民、事業者、地域組織及び関係機関がそれぞれの責務または役割を果たしていくことが大切です。
これらを踏まえ、市は、全ての市民が自分らしく地域でともに生きていくことができる環境を整え、現在及び将来にわたって認知症とともに生きる意識を高め、その備えをし、認知症の有無にかかわらず、安心していきいきと暮らせる地域共生社会の実現を目指して、この条例を制定します。
基本理念
次の3つを基本理念として定めています。
(1) 認知症の予防を含めた認知症に関する正しい知識及び理解に基づき、認知症の人及びその家族の視点に立った地域づくりを目指すこと。
(2) 認知症の人がその意思により、その有する力を最大限に活かしながら、安心して社会参加できる地域づくりを目指すこと。
(3) 認知症は誰もがなり得る身近な病気であるという認識の下、市、市民、事業者、地域組織及び関係機関はそれぞれの責務または役割を認識し、相互に連携して、全ての市民が認知症の有無にかかわらず、安心していきいきと暮らし続けることができる地域づくりを目指すこと。
施行日
令和4年3月29日
ダウンロード

- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康長寿福祉部 長寿福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0330 ファックス:0772-62-1156
お問い合わせフォーム
更新日:2022年04月15日