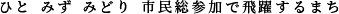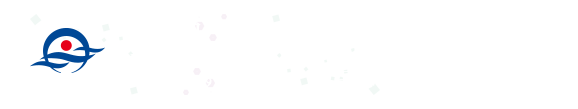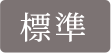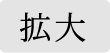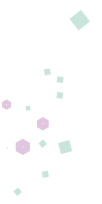4月29日 田植えスタート!
午前9時15分。
空には雲が薄く広がり、暑くも寒くもなくちょうど良い気候です。
ゴールデンウィーク3日目の今日、ついに田植えが始まりました!
農産グループでは田植機を共同で利用されているので、1週間程の田植えスケジュールを組んでメンバーの皆さんの田んぼで順番に作業していきます。
今日は記念すべきその初日。
田植えの方法を簡単に説明しますと、耕起や代掻きで使用したトラクターではなく、専用の田植機によって苗を移植します。
移植後は、肥料だけでなく稲の病気や害虫を防除するための薬剤、除草剤の散布を行います。
施肥管理(肥料のやり方)や農薬の処理体系は、同じ稲作でも作り手によって様々です。今回は田植えにあわせて全て同時に行っていきます。
さて、田植機に苗、肥料、薬剤、除草剤のセットが完了したら、いよいよ田植え開始です。
田植えをする際の一番のポイントは何か、の質問に対して・・・
「真っすぐ植えることだ」
と即答をいただきました。
真っすぐに植えると苗の生育管理がしやすいほか、今後の色々な作業に大きな影響が出てきます。
例えば、「溝切り(みぞきり)」。
6月中旬頃に田んぼの水を抜いて土を乾かす「中干し(なかぼし)」を行いますが、その際に苗と苗の間に入排水用の水路となる溝を作る作業が溝切りです。
苗が曲がっていると、この溝切りが非常にやりにくくなるそうです。
田んぼの中で機械を真っすぐに走らせることの難しさは先日体験済みなので、もう想像に難くありません。
真っすぐ植える、という言葉以上に技術を要する難しい作業です。
また、真っすぐ植えることだけに集中していればいいわけではありません。
植えるべき株が欠落していないか、肥料や除草剤はきちんと撒けているか、などにも気を配ります。
田植えは代掻きと同じで、基本的に同じ場所を走るのは一度きり。途中で欠株があってもその部分だけ田植機でやり直すことは出来ません。
そのほか、旋回や後進時にタイヤで苗を踏まないようにも注意します。
今日植えた苗は、これから収穫までの約4か月の長いお付き合いになります。
去年の京丹後の米作りは西日本豪雨以降の猛暑や、台風などによる長雨に悩まされました。
冬の降雪も例年よりかなり少なかったので、その影響か、早くも水不足気味の声も聞いていますが、9月には美味しいお米が収穫できるよう、今年は良い気候になることを祈っています!
田崎(農業振興課2年目)

一度に6条(列)ずつ移植していきます。苗と苗の株間は21センチ。日が当たりづらい田んぼでは、分げつ(ぶんげつ)と呼ばれる苗の株分かれ不足を補うため、18センチに狭めて密度を高めます。

苗は1株あたり3~4本。側条施肥(そくじょうせひ)と呼ばれる、移植と同時に苗の傍に肥料を埋め込む施肥方法により、作業の省力化を図ります。白や茶色の粒が肥料です。

根が張り巡らされた苗は一枚のマット状に。田植機にセットした苗が田んぼの途中でなくならないよう、畦(あぜ)に帰ってくる度にマット苗を補給します。1反あたり18枚使用しました。
 2反の田植えは1時間弱で終わりました。これが自分の田んぼだと、我が子を眺めるような心持ちでしょうか。大きく育て!
2反の田植えは1時間弱で終わりました。これが自分の田んぼだと、我が子を眺めるような心持ちでしょうか。大きく育て!
更新日:2019年05月13日