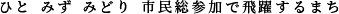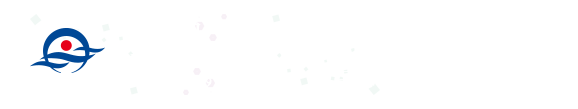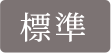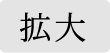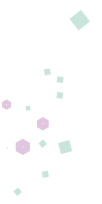後期高齢者医療制度の概要
制度の運営
後期高齢者医療制度は、京都府内のすべての市町村が加入する「京都府後期高齢者医療広域連合」が運営し、市町村と役割を分担し事務を行っています。
広域連合が行うこと
被保険者の認定や保険料額の決定、医療の給付など制度の運営を行います。
市町村が行うこと
被保険者への資格確認書の交付、各種届出や申請の受付、保険料の徴収や健康診査などを行います。
京都府後期高齢者医療広域連合ホームページはこちら(外部サイト)
被保険者
- 75歳以上の方(誕生日以降)と、一定の障害があり申請により認定を受けた65歳以上の方
※一定の障害がある65歳~74歳の人が障害認定を受け後期高齢者医療に加入する場合は、申請が必要です。またこの申請をした人はいつでも、申請の撤回をすることができます。
マイナ保険証
- 被保険者証として利用登録がされたマイナンバーカードです。利用登録は医療機関、薬局、市町村窓口やマイナポータルで行うことができます。
- 医療機関・薬局などで同意すれば、自己負担限度額の適用区分が適用されます。
資格確認書
被保険者には1人に1枚、「後期高齢者医療資格確認書」が簡易書留で郵送されます。(令和8年7月31日までの暫定運用)
この資格確認書には、負担割合「1割」、「2割」または「3割」が記載されています。医療を受けるときは、マイナ保険証または資格確認書を必ず提示して下さい。
負担割合
医療機関での負担割合は次のとおりで、前年の所得に応じて決まります。
| 一般 | 1割 |
住民税課税所得が28万円未満 |
|---|---|---|
|
一般2 |
2割 |
同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる場合
|
| 現役並み 所得者 |
3割 | 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる場合 但し、年収が次の場合は申請により「一般」となります。
|
入院されたときの食事代
入院されたときは、食費として次の標準負担額を自己負担します。(令和7年4月診療分以降)
| 現役並み所得者・一般(下記以外の人) | 510円 (補足1) |
|
|---|---|---|
| 低所得2.(住民税非課税世帯) | 90日以内の入院(過去12カ月の入院日数) | 240円 |
| 90日を超える入院(過去12カ月の入院日数) | 190円 (補足2) |
|
| 低所得1. (住民税非課税世帯で、かつ各所得が必要経費・基礎控除を差し引いたときに0円となる人または老齢福祉年金を受給している人) |
110円 | |
【療養病床】(令和6年6月1日から)
| 1食当たりの食費 | 1日当たりの居住費 | |
|---|---|---|
|
現役並み所得者・一般(下記以外の人) |
510円(補足1) | 370円 |
| 低所得2. | 240円 | 370円 |
| 低所得2.(過去12カ月で90日を超える入院) | 190円(補足2) | 370円 |
| 低所得1. | 140円 | 370円 |
| 低所得1.(老齢福祉年金受給者) | 110円 | 0円 |
(注意)低所得1.2.に該当する人は、入院の際にマイナ保険証または適用区分が併記された資格確認書が必要です。適用区分の併記は保険事業課または市民局窓口で申請してください。
(補足1)指定難病の方は300円です。平成28年3月31日において、すでに1年以上継続して精神病床に入院中で、その後も継続して何らかの病床に入院している方は、260円です。
(補足2)申請月以前12カ月間に低所得2.の状態で入院日数が90日を超え、申請し、認定された場合は190円(京都府の後期高齢者医療制度に加入する前の保険で低所得2.だった期間の入院日数も合算できます)。
医療費が高額になったとき
1ヶ月の医療費が高額になったときは、申請をすると(申請は初回のみ必要)、自己負担額を超えた分が払い戻しされます。
| 区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | ||
|---|---|---|---|---|
|
現役並み所得者 (3割) |
現役3.(課税所得690万円以上) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が140,100円となります。 ) |
||
|
現役2.(課税所得380万円以上) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が93,000円となります。 ) |
|||
|
現役1.(課税所得145万円以上) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が44,400円となります。 ) |
|||
| 一般(1割) |
18,000円 (年間の上限144,000円) |
57,600円 (過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が44,400円となります。 ) |
||
| 住民税非課税世帯 | 低所得2. | 8,000円 | 24,600円 | |
| 低所得1. | 8,000円 | 15,000円 | ||
令和4年10月1日から令和7年9月30日まで
| 区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | ||
|---|---|---|---|---|
|
一般2 (2割) |
18,000円 または「6,000円」+(医療費-30,000円)×10%」の低い方を適用 |
57,600円 (過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が44,400円となります。 ) |
||
自己負担限度額適用区分等の併記について
対象となる方で資格確認書に併記がない場合は、受診の前に保険事業課または市民局窓口で申請をしてください。
限度額適用認定区分
高額な保険診療を受けたときの医療機関等の窓口での支払い(入院時の食事負担や差額ベッド代等は除く)を高額療養費の自己負担限度額までとすることができます。
- 対象となる方は、上限額一覧の表中、現役並み所得者の現役2.または現役1.
限度額適用・標準負担額減額認定区分
限度額適用認定区分に加えて、入院時の食事代を減額することができます。
- 対象となる方は、上限額一覧の表中、住民税非課税世帯の低所得2.または低所得1.
なお、限度額適用・標準負担額減額認定区分の併記があり、住民税非課税世帯の低所得2.に該当する方の場合、申請月以前の12か月間で入院日数が90日を超えたときは、医療機関等で長期該当年月日の記載のある資格確認書を提示すると入院時の食事代がさらに減額されます。(長期該当年月日の記載は、再度申請が必要となります。)
申請に必要なもの
- 資格確認書
- 個人番号カードまたは個人番号の通知カード
特定疾病について
厚生労働大臣が定める特定疾病の自己負担限度額(月額)は、10,000円です。
- 人口透析が必要な慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
該当される方は、医療機関で「特定疾病療養受領証」を提示する必要がありますので、申請をしてください。
申請に必要なもの
- 資格確認書
- 医師の意見書、自立支援医療受給者証、直前に加入していた医療保険の特定疾病受領証のいずれか1点
- 個人番号カードまたは個人番号の通知カード
医療費の払い戻しが受けられる場合
次のような場合で、医療費を一旦全額自己負担したときは申請して認められると、自己負担分を除いた額が支給されます。
やむを得ず資格確認書を使わないで診察を受けたとき
申請に必要なもの
- 資格確認書
- 診療報酬明細書
- 領収書(原本)
- 申請者の振込先がわかる通帳など
- 個人番号カードまたは個人番号の通知カード
海外で診察を受けたとき
申請に必要なもの
- 資格確認書
- 診療内容明細書
- 領収明細書
- 日本語翻訳文
- パスポート
- 同意書
- 申請者の振込先がわかる通帳など
- 個人番号カードまたは個人番号の通知カード
骨折・脱臼などで、柔道整復師の施術を受けたとき
申請に必要なもの
- 資格確認書
- 施術内容明細書
- 領収書(原本)
- 申請者の振込先がわかる通帳など
- 個人番号カードまたは個人番号の通知カード
医師が必要と認めた、はり・灸・あんま・マッサージなどを受けたとき
申請に必要なもの
- 資格確認書
- 施術内容明細書
- 医師の同意書
- 領収書(原本)
- 申請者の振込先がわかる通帳など
- 個人番号カードまたは個人番号の通知カード
医師の指示によりギプス・コルセットの医療器具を購入したとき
申請に必要なもの
- 資格確認書
- 医師の意見書・装着証明書
- 領収書(明細が分かるもの、原本)
- 申請者の振込先がわかる通帳など
- 個人番号カードまたは個人番号の通知カード
移送費
移送が困難な重病人が緊急的にやむを得ず医師の指示により転院などの移送に費用がかかったときに、広域連合が必要と認めた場合に支給されます。
訪問看護療養費
医師の指示により訪問看護ステーションなどを利用した場合、費用の一部を支払うだけで、残りは広域連合が負担します。
葬祭費
被保険者の方がお亡くなりになったときは、葬祭を行った方に対して、葬祭費として50,000円を支給します。
申請に必要なもの
- 葬祭執行者の身分証明書
- 葬祭を行ったことが確認できる書類(葬祭の領収書や会葬お礼のはがき等)
- 葬祭執行者の振込先がわかる通帳など
保健事業(人間ドック)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民環境部 保険事業課
〒627-8567
京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0220 ファックス:0772-69-0901
お問い合わせフォーム
更新日:2025年07月10日