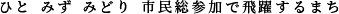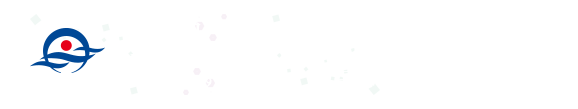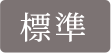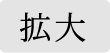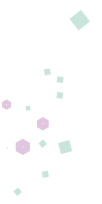国民健康保険税の決まり方
1.国民健康保険税について
国民健康保険(国保)は、病気やけがをしたときに安心して治療を受けることができるよう、国保加入者が保険税を負担し、必要な医療費に充てて相互に助け合う医療保険制度です。
納税義務者は世帯主です
国保税は、世帯主が国保に加入していなくても同じ世帯で国保に加入しているかたがいれば、世帯主が納税義務者となり、国保税を納めることになります。(擬制世帯主)
ただし、国保税がかかるのは加入者分のみです。
2.国保税の決まり方
国保税は、加入者の年齢によって決まり方が異なります。
|
40歳未満 |
「医療分」+「支援金分」=国保税 (介護分の負担はありません。) |
|
40歳~64歳 介護保険の |
「医療分」+「支援金分」+「介護分」=国保税 (同じ世帯の40歳~64歳の方以外の所得などは、介護分の計算に影響しません。) |
|
65歳~74歳 介護保険の |
「医療分」+「支援金分」=国保税 (介護分は別に介護保険料として納付。) |
国保税は年度ごと(4月から翌年3月)に計算します
年度の途中で、加入者数や所得などに変更のあった場合は変更届の翌月に再計算し、変更後の納税通知書を郵送します。
【年度途中で加入・脱退した場合の国保税の計算】
|
年度途中で加入した場合 |
加入した月の分から国保税がかかります。月割で計算し納税(変更)通知書を郵送します。 |
|
年度途中で脱退した場合 |
脱退した月の前月まで国保税がかかります。月割で計算し納税(変更)通知書を郵送します。納めすぎの税金がある場合は還付します。 |
|
年度途中で40歳になった場合 |
40歳になった月から介護分を納付していただきます。変更後の納税(変更)通知書を郵送します。 |
|
年度途中で65歳になった場合 |
年度当初から、65歳になる月の前月分までの介護分を計算し、月割にしています。 |
|
年度途中で75歳になった場合 |
年度当初から、75歳になる月の前月分までの国保税を計算し、月割にしています。75歳からは後期高齢者医療保険制度に加入し、別に納めることになります。 |
世帯の所得などをもとに計算します
| 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | |
| 医療分(全加入者対象) | 6.56% | 9.55% | 19,000円 | 30,700円 |
| 支援金分(全加入者対象) | 2.22% | 3.20% | 6,200円 | 10,700円 |
| 介護分(40歳以上64歳まで) | 2.10% | 3.25% | 7,900円 | 9,300円 |
国保税の計算方法:所得割・資産割・均等割を算出した後に平等割を加えた額となります。
【用語説明】
・所得割・・・国保加入者の前年中の総所得金額等(注1)に応じて計算します。
注1※前年中の総所得金額、分離短期・長期譲渡所得、株式等譲渡所得等、先物取引雑所得等、上場株式等の配当所得等、山林所得等の合計額から基礎控除43万円を控除した額。
・資産割・・・国保加入者の固定資産税額(償却資産を除く)(注2)に応じて計算します。
注2※共有名義分がある場合は持分割合で計算します。償却資産分を除きます。
・均等割・・・国保加入者の人数に応じて計算します。
・平等割・・・国保加入世帯ごとに定額で計算します。
注3※被保険者が後期高齢者医療制度に加入することにより単身被保険者世帯となった世帯(特定世帯)は、世帯状況に変更がない場合、以後5年経過する月分まで、医療分・支援金分の平等割額を2分の1軽減します。さらに、その後も世帯状況に変更がない場合、3年経過する月分まで、医療分・支援金分の平等割額を4分の1軽減します。
課税限度額は、医療分66万円、支援金分 26万円、介護分 17万円です。
(令和7年度税制改正により、医療分の限度額が65万円から66万円に、支援金分の限度額が24万円から26万円に引き上げられました。)
令和7年度から国民健康保険税の算定方法が変わります
国保税の資産割を廃止し、算定は4方式から3方式へ

【資産割を廃止する主な理由】
少子高齢化が進み、国保税が課税される世帯は年金受給者をはじめとする高齢者が6割を超える中、収益性のない居住用資産にも課税されることや市外に所有する固定資産が算定に含まれないこと、また、国保以外の被用者保険制度には資産割がないなど、公平性の面から制度的な均衡を保つ上で課題があったことから、全国的に資産割を廃止する市町村が増えています。これらの状況をもとに、京丹後市国民健康保険運営協議会の答申も踏まえ総合的に判断し、廃止することとしました。
※算定方式の変更に伴い、令和6年度と比べて税額が上がる世帯と下がる世帯がありますが、ご理解とご協力をお願いします。
| 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | ||
| 医療分 (全加入者対象) |
令和6年度 | 6.54% | 19.10% | 21,200円 | 22,400円 |
| 令和7年度 | 6.56% | 9.55% | 19,000円 | 30,700円 | |
| 支援金分 (全加入者対象) |
令和6年度 | 2.20% | 6.40% | 7,200円 | 7,600円 |
| 令和7年度 | 2.22% | 3.20% | 6,200円 | 10,700円 | |
| 介護分 (40歳以上64歳まで) |
令和6年度 | 2.10% | 6.50% | 9,600円 | 6,600円 |
| 令和7年度 | 2.10% | 3.25% | 7,900円 | 9,300円 |
国保税の計算方法:所得割・資産割・均等割を算出した後に平等割を加えた額となります。
18歳までの均等割の全額軽減
条例では、令和4年4月から小学校入学前の子どもの均等割は2分の1が減額となっていますが、今回の算定方法の変更に伴い子育て世帯の負担軽減を図るため、京丹後市独自の施策として18歳に達する日以後の最初の3月31日までの均等割全額を減額します。
3.国保税の納め方
国保税の納税方法は、「普通徴収」(口座振替や納付書)と、「特別徴収」(年金天引き)の2種類です。
普通徴収の場合
6月から翌年3月までの10回に分けて納付していただきます。
【納付書による納付】
納税通知書に同封の納付書で、納期限までに納付してください。納付場所は納付書の裏面に記載しています。
【口座振替による納付】
全期前納振替と期別振替があります。全期前納振替を申し込まれているかたは、1期の振替日に全期分を一括振替します。
(注意)1期に残高不足等により振替ができなかった場合は再振替以降期別納付に変わりますのでご了承ください。
特別徴収の場合
年6回の年金から天引きさせていただきます。
国保に加入している世帯員全員(世帯主を含む)が65歳から74歳のかたで、次の2つの条件を満たす場合、国保税は世帯主の年金からの天引き(特別徴収)となります。
- 世帯主の年金支給額が年額18万円以上の場合
- 世帯主の介護保険料と国保税の合計額が年金支給額の2分の1を超えない場合
上記以外の場合、または納付方法変更申出書の提出のあったかた、または世帯主が75歳になる年度は普通徴収となります。税額変更があった場合にも一時的に普通徴収となることがあります。
納付方法(特別徴収から口座振替)の変更について
今後の国保税を口座振替で納付していただける場合、申し出により特別徴収を中止し、納付方法を口座振替に変更することができます。変更を希望される場合は、税務課または市民局窓口へお申し出ください。
- 国保税の滞納があるかたについては、納付方法の変更が認められない場合があります。
- お申し出いただく時期により変更月が異なります。
4.国保の届出について
国保に加入するとき、もしくは脱退するときは、14日以内に保険事業課または市民局窓口に届出を行ってください。
詳しくは、「国民健康保険制度のページ」をご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民環境部 税務課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0180 ファックス:0772-69-0901
お問い合わせフォーム
更新日:2025年05月29日